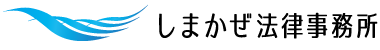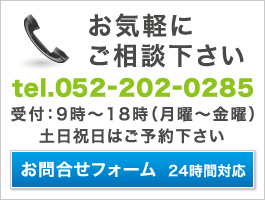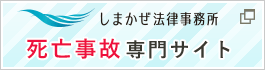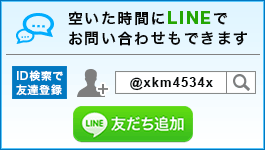Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(49)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(49)
15.定期金賠償が問題となった事例
(肯定例)
・ 脳挫傷,びまん性軸索損傷等で高次脳機能障害3級の幼児(固定時12歳)につき,不法行為に基づく損害賠償制度の,被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利益を補填して,不法行為がなかったときの状態に回復させるとの目的と損害の公平な分担という理念に照らし,将来において取得すべき利益の損失が現実化する都度これに対応する期間にその利益に対応する定期金の支払いをさせるとともに,将来,算定の基礎となった後遺障害の程度,賃金水準その他の事情に著しい変更が生じ,算定した損害の額と現実化した損害の額との間に大きなかい離が生ずる場合には,民訴法117条によりその是正を図ることができるようにすることが相当とし,逸失利益につき定期金賠償を命ずるに当たっては,交通事故の時点で,被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,就労可能期間の終期より前に被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しないとして,定期金賠償方式を採用し,固定年の賃金センサス男性学歴計全年齢平均を基礎に,就労可能年に達する日から67歳に達する日まで,月額44万円余を認めた。
(否定例)
・ 高次脳機能障害(5級),嗅覚障害(12級),醜状障害(7級)の併合3級の会社員(固定時28歳)の逸失利益につき,いわゆる「継続説」や,後遺障害の内容・程度が将来の介護費用と一体のものとして定期金賠償を認め得る場合ではないこと,被害者が定期金による支払を求めているのが症状固定後15年間のみでその合理的理由が不明なこと等から,定期金賠償方式によるべき合理性及び必要性があるものとは認められない。
・ 父経営の会社に後継者として勤務する男(固定時31歳)の遷延性意識障害等(1級)につき,後遺障害及び労働能力喪失の程度が将来重篤化することは考え難いこと,他方,労働能力喪失の程度が将来的に逓減されることも想定されておらず,将来の現実収入が現時点で算定する収入を上回る事態を想定し得ないこと等から,定期金賠償が相当と認められる場合には当たらない。
・ 大学院生(固定時24歳)の高次脳機能障害等(9級)につき,後遺障害の程度が今後大きく変化するのは考え難いこと,賃金水準等の変化が逸失利益に与える影響は限定的であること,自らの労働で相当程度の収入を得ることが可能であって定期金の必要性も高いとはいえないこと等から,定期金賠償が相当とまでは認められない。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(48)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(48)
13.その他の障害
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例
・ 会社員(固定時57歳,右下肢短縮13級)につき,事故による輸血で発症したC型肝炎(自賠責非該当)を12級に該当するとして,併合11級とし,10年間15%の労働能力喪失を認めた。
14.後遺障害を負った被害者が死亡した事例
・ 6級相当の後遺障害を残した被害者(44歳)が,症状固定後,当該事故と相当因果関係のない水難事故により死亡した場合につき,死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきではないとし,逸失利益は死亡時までに限るとした原審判決を破棄した。
・ 12級の後遺障害を残した被害者(高校生)が,症状固定後,当該事故と因果関係のない別件交通事故で死亡した場合につき,死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきではないとして,死亡後の逸失利益を認め,かつ,死亡後の生活費控除を否定した。
・ 第5胸髄以下完全麻痺の被害者(固定時21歳)が,交通事故と因果関係の認められる自殺をした場合に,死亡逸失利益算定において,被害者が独身であることから生活費控除率を50%とした。
・ 兼業主婦(死亡時55歳)が,事故により頭部外傷,脳挫傷等の傷害を負い,症状固定前に自殺した事案で,主位的に死亡による損害賠償,予備的に後遺障害による損害賠償を主張して算出された損害額のうち多い方を請求した場合に,事故と自殺との間に相当因果関係があるから,死亡による損害賠償と併せて後遺障害による損害賠償請求をすることは許されないとして,死亡による逸失利益を認めた。
・ 会社員(固定時22歳)が遷延性意識障害等により1級3号の後遺障害を残し,症状固定後約2年で死亡し,事故と死亡との間に相当因果関係が認められない場合につき,生活費控除を行うべきとの被告主張を斥けて,45年間100%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:年末年始の交通事故にお気を付け下さい
愛知県警察によると,令和3年12月22日現在,交通事故による死者数は134人となっており,昨年より20人多くなっています。
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou221222.pdf
愛知県内では,例年,12月が交通死亡事故が最も多くなっていますので,年末に向けて,更なる安全運転が求められます。
また,強烈な寒波により日本海側では大雪となっている地域があります。年末年始にかけても引き続き大雪の予報が出ていますので,帰省やレジャーなどで車を運転される方は,最新の情報を確認した上で,より安全を心がけて運転してください。
普段あまり雪が降らない地域に住んでいる場合,冬用のタイヤを用意していないことも多いですが,ノーマルタイヤで雪道を走行する行為自体が交通違反となります。
また,大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪があるときには「チェーン規制」が発令されますが,「チェーン規制」が発令された場合は,スタッドレスタイヤをつけていたとしても、その上からチェーンを装着しないと走行できません。
雪道であるにもかかわらず冬用のタイヤやチェーンを装着していない場合は,事故発生時,過失割合が加算される場合がありますので,注意が必要です。
では,もし年末年始に交通事故の被害に遭ったら,どうすれば良いでしょうか。
交通死亡事故の場合,お亡くなりになられた方が一家の大黒柱ですと,早急な金銭的サポートが必要になることもあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,直接,自賠責に保険金を請求し,まず自賠責の範囲内で保険金を獲得し,最終的に弁護士基準との差額を請求しています。2段階の手続きを行うことで早急な金銭回収が可能となり,ご遺族が生活費等でお困りになる危険を回避します。
ご家族が死亡事故に遭われお困りの方は,ぜひ,早期にご相談ください。
お怪我をされた場合,年末年始は医療機関が休診していたり,忙しくて医療機関に受診ができない,交通事故から数日後に痛みが生じたなど,気づいたときには事故から2週間以上経過していることもあります。
この場合,相手方の保険会社やご自身が加入している人身傷害保険に対して,医療機関への受診を希望しても,事故から2週間以上経過している場合は,初診遅れによる因果関係なしと治療費の対応を拒絶されることがほとんどです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,初診遅れで治療費の対応を拒絶された場合,初診遅れの意見書を添付の上で,直接,自賠責に治療費や慰謝料などを請求し,保険金を回収しています。
また,後遺症が残る事案では,保険会社からの賠償額の提示を待ってから弁護士に相談していては遅い場合があります。
いつ依頼されても弁護士の費用に変わりはありませんので,適正な賠償額で解決するためにも,ぜひ,早期にご相談ください。
その他,交通量が増えることで,「あおり運転」の被害に遭う可能性もあります。
もし,「あおり運転」の被害に遭ったら,まずは,サービスエリアやパーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難して,警察に110番通報をしてください。また,「あおり運転」の加害者から暴行を受けないように,車のドアや窓をロックし,車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり,事故によってケガをした場合は,損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」の立証には,ドライブレコーダーが有効になりますので,ドライブレコーダーの取付をお勧めします。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では,ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して,「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし,適正な過失割合で事故の解決をしていますので,お困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(47)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(47)
12.上肢・下肢・及び手指・足指の障害
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例(3)
・ 運送会社代表(固定時47歳)の右上肢の色素沈着(14級),右肩腱板断裂後の右肩関節機能障害(非該当)につき,自賠責認定基準には至らないが,軽度の可動域制限が残存していること,事故前に比べ,重い物が持てなくなり,パソコン操作や運転操作をするに当たって右肩が異常に凝るなどして,仕事に支障が出ていること等から,67歳まで5%の労働能力喪失を認めた。
・ 有職主婦(固定時54歳)の右膝関節機能障害(12級)につき,右膝について,脛骨高原骨折だけではなく,前十字靱帯,後十字靱帯,外側支持機構の複合靱帯損傷を合併した重篤な骨折脱臼を生じており,客観的には,動揺性があり,常時硬性補装具を必要とする状態であったことから,右膝関節の用廃(8級)に該当するとして,14年間45%の労働能力喪失を認めた。
・ 工場勤務(固定時22歳)の生殖器障害・骨盤骨変形(疼痛含む,11級相当),左股関節機能障害(12級)の併合10級につき,5つの機能障害が併存し,立位や座位を数時間に渡って保持する必要のある職種への就業は容易でない等から,67歳まで30%の労働能力喪失を認めた。
・ 潜水艦タンク内装塗装業務従事者(固定時28歳)の右腰部臀部痛(14級)につき,右下肢の後遺障害について他覚的所見を認めることはできないが,事故により右足による自立が困難なため,常に長下肢装具を装着し,松葉杖を使用せざるを得ず,事故当時の勤務先を退職後,就労できず職業訓練学校に通っているといった生活状況に加え,症状経過から画像に現れていないが腰部神経根の損傷があったと推測される等の診断内容をも総合考慮すると,右下肢の麻痺による機能障害が残存したとし,その程度は1下肢の3大関節中の1関節の用廃(8級)と同程度として,67歳まで45%の労働能力喪失を認めた。
・ リフォーム業(固定時74歳,併合14級)につき,事故前から無症状の腱板断裂を発症していた,関節可動域角度の悪化は不自然との加害者側の主張を敗訴し,右肩腱板損傷後の右肩関節機能障害は10級にがいとうするとし(併合10級),平均余命の半分(6年間,27%の労働能力同率を認めた。)
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(46)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(46)
12.上肢・下肢・及び手指・足指の障害
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例(2)
・ 配管設備業(固定時62歳)の左膝関節機能障害,左下肢の神経症状等(10級)につき,左膝の障害が著しいため歩行能力が著しく制限され,階段の昇降はもちろんのこと,杖を使用しても短距離かつ短時間の歩行しか行えないことを考慮し,10年間40%の労働能力喪失を認めた。
・ 派遣ミキサー車運転手兼鉄道保全軌道工(固定時37歳)の右手月状骨骨折等による右手関節痛を含む右手関節の可動域制限(12級6号)につき,症状固定時点で健側の52%とほぼ2分の1に制限されていること,当初から障害の憎悪が見込まれており実際に1年後には健側の32%に憎悪していることからすると10級10号に相当するとして,67歳まで27%の労働能力喪失を認めた。
・ 高等学校事務職員(固定時29歳,右鎖骨変形障害12級,右肩関節可動域制限10級,右頸部外貌醜状12級,併合9級)につき,右上肢の障害による労働能力喪失の程度は8級相当に至らないとしても,それに相当近いものがあるとし,右鎖骨変形障害は12級5号に該当することも併せ,67歳まで45%の労働能力喪失を認めた。
・ バス運転手(固定時48歳)の右母趾基部底側の痛み(14級)につき,同部の痛み,右膝関節外側の痛みのほか,右母趾の屈腱筋損傷等によるMP関節及びIP関節の屈曲が困難であるなどの関節可動域制限が残存したとし,67歳まで14%の労働能力喪失を認めた。
・ 歯科勤務医(固定時40歳)の左肩関節機能障害(10級),脊柱変形(11級)の併合9級につき,左肩の可動域制限及び左肩痛が原因となって,左手指による患歯の固定が行えず,今後歯科医として稼働する可能性を閉ざされたというべきであるとして,67歳まで70%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社員(固定時27歳)につき,左肘関節機能障害(12級),右手指関節機能障害(11級),左足関節機能障害(12級),右足指関節機能障害(11級)等に加え,事故後8年後に発症したPTSD(14級)を考慮し,併合9級としつつ,右下肢のみでも9級相当と評価されるのに四肢に後遺障害がある本件を同列に扱うことはできないとして,67歳まで45%の労働能力喪失を認めた。
・ 歯科開業医(固定時56歳)の右肩打撲後の疼痛(14級)につき,外形的に明らかな器質的損傷は認められない場合であっても関節包が侵襲を受け痛み等の理由で関節を動かせないでいると組織侵襲部位に癒着形成を招き関節包の繊維化が生じることで関節拘縮が生じ得るとしたうえ,10級10号に該当する可動域制限が残存したと認定し,13年間27%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(45)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(45)
12.上肢・下肢・及び手指・足指の障害
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例(1)
・ 中学1年生男子の左環指開放骨折による爪の変形,循環障害(非該当)につき,OA機器を効率的に利用するには手の10指が十分に機能することが望ましいとして,18歳から67歳まで,2%の労働能力喪失を認めた。
・ 自動車車体改造業者(固定時31歳,右下肢短縮等13級)につき,右膝関節機能障害につき自賠責認定基準の運動可能領域よりわずか2.5度広く可動するものの右脛腓骨変形癒合等が認められることから12級7号に相当し,併合11級相当として,67歳まで20%の労働能力喪失を認めた。
・ 鍼灸マッサージ業者(49歳)の左上肢,左膝の障害(併合14級)及び多少あった視力の完全喪失(非該当)につき,17年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 被害者(固定時67歳,骨盤骨変形12級)の左膝関節機能障害(非該当)につき,可動域は基準に達していないが,日常生活において極めて困難を来している面があるとして12級7号を認め,併合11級とし,9年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 被害者(固定時45歳)の右下肢1センチ短縮,約30度の外旋変形(12級)につき,立位での荷重バランスが悪く1時間以上起立不能で,時間給のアルバイトの職にしかつくことができず事故前より収入が大幅に減収したとして,67歳まで20%の労働能力喪失を認めた。
・ 造園業手伝い(固定時52歳)の右膝半月板損傷による運動・労作後の関節水症,四頭筋萎縮,右膝外側関節裂隙の圧痛(12級)につき,これまで肉体的作業に従事してきたことや収入減少の見込み等を考慮し,10年間25%の労働能力喪失を認めた。
・ ホテル勤務の和食調理師(固定時51歳)の右足関節障害等(12級)につき,しゃがめない,自由に足底をついて歩けない,3時間以上の立位で足の痛みとしびれが生じる等,立位で行う板前の職業に相当の影響があり,転職も年齢から制限されるなどとして,67歳まで20%の労働能力喪失を認めた。
・ 鍼灸指圧師(固定時70歳)の右肩関節可動域制限,右上肢のしびれ等(12級)につき,治療業務においては指先を使うばかりでなく手指を患者の体に当てた上で手指に対する体重のかけ方を微妙に調整するなど,施術を行う上で肩関節障害の影響は大きいとし,5年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ 農学部造園科を卒業し造園設計の仕事に携わってきたアルバイト(固定時27歳)の前腕部の知覚鈍麻,しびれ等(12級)につき,腕関節の可動域制限は参考運動が制限されているにすぎないとしながら,造園設計の業務に相当の影響があるとして,67歳まで20%の労働能力喪失を認めた。
・ タクシー運転手(固定時65歳)の右肩,左膝,左足の各関節機能障害,下肢の疼痛等(併合8級)につき,長時間一定の姿勢を取ることを強いられる職業運転手としての業務はほぼ不可能となったとして労働能力喪失率を60%とし,狭心症の既往症がある被害者が肉体的に過酷な勤務を余命期間の半分継続できるか疑問として7年間を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】12月は業務中,通勤時の死亡重傷事故が年間最多
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると,12月は交通死亡事故が多発しています。12月中の交通死亡事故の特徴としては,①歩行者事故として,【年齢】高齢者が6割以上,【時間帯】朝及び夕方から深夜にかけて多発です。②自転車事故として,【年齢】高齢者が約9割,【事故類型】出合い頭が約6割,【時間帯】9時台から13時台が約6割となっています。
また,業務中,通勤時の死亡重傷事故が年間最多となっています。年末は業務多忙となり心身の疲れなどが運転に影響を及ぼすことが予想されますので,体調管理に努めるとともに,時間にゆとりを持ち,速度を控え,安全行動を心掛けることが大切です。
(https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/20221019point.pdf)
業務中・通勤時に交通事故の被害に遭った場合,労災保険から保険給付を受けることができます。業務時間中の事故は業務災害,通勤退勤の途中の事故は通勤災害となります。 労災保険で受けることができる給付は,①療養(補償)給付,②休業(補償)給付,③障害(補償)給付,④傷病年金,⑤介護(補償)給付,⑥遺族(補償)給付,⑦葬祭料があります。
労災保険を使用するメリットとしては,治療費を全額支給してもらえることです。自賠責保険の場合は限度額が120万円となっており,加害者の任意保険会社が支払っている場合も治療期間が長くなると治療費の支払いを打ち切るケースが多くあります。労災保険には限度額や打ち切りがないため,安心して最後まで治療を受けることができます。
また,休業損害・補償を多く受けることもできます。労災保険を使用する被害者に休業損害が発生した場合,労災保険から給付基礎日額の60%が休業(補償)給付と支給され,残りの40%を保険会社に請求します。
それとは別に社会復帰促進等事業の一環として,給付基礎日額の20%にあたる休業特別支給金を受け取ることができます。休業(補償)給付や保険会社から支払われた休業損害を既に受け取っていた場合,保険会社に対する損害賠償額から控除されますが,休業特別支給金は控除されません。
同様に,後遺障害が残存したときに支給される障害特別支給金も,損害賠償額から控除されません。
さらに,費目間の流用を禁止するルールがあるため,積極損害,消極損害,慰謝料で各費目分類し,各費目の過失相殺後の残額は,いずれも当該費目間に関してのみ既払金及び損益相殺で補填されます。
(例)
過失割合が加害者:被害者=70:30,治療費100万円,休業損害100万円,慰謝料100万円,労災から療養給付100万円,休業給付60万円受給している場合
治療費は,過失相殺すると100万円×70%=70万円となり,損益相殺すると70万円-100万円=-30万円となり,保険会社に請求できる治療費は0円となります。
休業損害は,過失相殺すると100万円×70%=70万円となり,損益相殺すると70万円-60万円=10万円となり,保険会社に請求できる休業損害は10万円となります。
慰謝料は,労災保険の支給対象外なので差し引かれる給付はなく,保険会社に請求できる慰謝料は過失相殺した100万円×70%=70万円となります。
治療費が30万円過払いとなっていますが,費目間の流用が禁止されているため,他の費目から控除されることはなく,保険会社に請求できる賠償額は,0万円+10万円+70万円=80万円となります。
仮に労災保険を使用せず,保険会社の一括対応で自由診療による治療をしていた場合は,過払いとなった治療費が他の費目から控除されるため,-30万円+10万円+70万円=50万円となります。
以上のとおり,労災保険を使用するメリットは多くありますが,損害賠償額の計算方法など複雑な部分もあります。
弁護士法人しまかぜ法律事務所は,労災保険を使用した交通事故の解決実績が豊富にありますので,労災保険を使用する交通事故でお困りの方は,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(44)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(44)
12.上肢・下肢・及び手指・足指の障害
上肢の後遺障害は,①欠損障害として1~5級,②機能障害として1~12級,③変形障害として7~12級があります。
下肢の後遺障害には,①欠損障害として1~7級,②機能障害として1~12級,③変形障害として7~12級,④短縮障害として8~13級があります。一般的には,受傷した方の脚が他方の脚より短くなりますが,年少者などにおいては逆に健全な脚より長くなる過成長になることもあります。その場合も短縮障害に準じる障害として扱われます。
手指の後遺障害は,①欠損障害として3~14級,②機能障害として4~14級があります。
足指の後遺障害は,①欠損障害として5級~13級,②機能障害として7級~14級があります。
機能障害の原因は器質的損傷(骨折後の癒合,関節拘縮,神経の損傷)であることを証明する必要があり,疼痛による可動域制限(痛いから曲げられない)では,神経症状と認定され,低い等級(12,14級)に認定されやすいです。
(1)認定例
・ 被害者(事故時9歳,固定時18歳)の左大腿骨変形癒合12級,左下肢瘢痕14級の併合12級につき,足に負担が掛かると考えられる美容師として稼働をしていること等に照らし,67歳まで14%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社員(固定時28歳)の左膝痛等の症状を伴う左腓骨変形障害12級につき,足に大きな負担がかかる仕事を担当しており,受傷後の足の痛みや足関節の可動域の定価等の症状は,その仕事内容に具体的な影響を及ぼすものとして,67歳まで14%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(43)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(43)
11.脊柱及びその他の体幹骨の障害
脊柱及びその他の体幹骨の障害は,①脊柱の変形障害,②脊柱の運動障害,③その他の体幹骨(鎖骨,胸骨,ろく骨,肩こう骨,骨盤骨)の変形障害に分けられます。
①脊柱の変形障害は,その変形の程度により6級,8級,11級に認定されます。②脊柱の運動障害は,脊柱圧迫骨折等に基づく頚部および胸腰部の硬直や可動域制限,または荷重障害の程度により6級,8級に認定されます。③その他の体幹骨の変形障害は12級が認定されます。裸体になった時に変形や欠損が明らかにわかる程度のものを指すため,レントゲン撮影などによってはじめて確認できる程度のものは該当しません。
(1)認定例
・ 特殊運搬船の運航管理者(固定時56歳)の脊柱変形(11級),左脛骨近位端関節内骨折後の左膝痛(12級)の併合10級につき,船上等に出向く機会が多く,船長として乗船勤務の予定があるところ,症状により乗船勤務ができなくなる可能性や長時間の乗船勤務が必要な高い収入の得られる船の船長になれないおそれがある等から,事故前の年収を基礎に,13年間27%の労働能力喪失を認めた。
・ 特殊事務所職員(固定時48歳)の第一腰椎圧迫骨折後の脊柱変形(11級)につき,日常生活においては腰に過度の負担がかからないように注意する必要があり,腰に負担がかかるスポーツ等も控えなければならない等として,事故前年の年収を基礎に19年間20%の労働能力喪失を認めた。
・ トラック運転手(固定時37歳)の右鎖骨変形(12級)につき,同障害には重い物を持ち上げたり下ろしたりするときの痛み等の症状も含まれており,業務に影響が生じていること等から,67歳まで14%の労働能力喪失を認めた。
・ 会社員たる現場監督(固定時54歳)の左肩関節機能障害等(併合9級)につき,左鎖骨の変形障害が原因とみられる疼痛が続いていること,裸体になったときに変形が明らかにわかる程度のものであること等に照らすと変形障害についても実際に労働能力を喪失させていると評価できるとして,14年間35%の労働能力喪失を認めた。
・家事従事者(固定時52歳)の軸椎骨折後の脊柱変形(11級),左足部痛,歩行時痛(14級)の併合11級につき,左足部痛,歩行時痛等は12級13号に該当するとして,併合10級とし,67歳まで27%の労働能力喪失を認めた。
・ 清掃業従事者(固定時45歳)の第五腰椎変形骨折後の脊柱変形(11級)につき,変形の程度が大きいこと,従事する清掃業で腰部への負担が重いことから,22年間20%の労働能力喪失を認めた。
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例
・ 運送会社会社員(固定時59歳)の咀嚼機能障害(非該当),脊柱の運動障害(11級),胸腰椎部の運動障害(非該当),口が開きにくい,物が咬みにくいとの症状(14級)の併合11級につき,咀嚼機能障害等は労働能力に影響しないが,脊柱の運動障害等は労働能力に影響すること,腰背部痛のために,重いものを持ったり長時間の座位,歩行等が困難等の支障を生じていること,後遺障害のため事故後は稼働していないことから,11年間45%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
変形障害のうち,特に鎖骨の変形障害は労働能力に影響しないと保険会社から主張され,逸失利益が否定されることもあります。弁護士法人しまかぜ法律事務所では,変形障害から派生する疼痛障害と併せて労働能力への影響を主張し,逸失利益が認定されるケースが多くあります。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:消極損害その2 後遺障害逸失利益(42)
交通事故の被害に遭い,加害者へ請求できる損害賠償には,積極損害,消極損害,慰謝料があります。
積極損害とは,事故により被害者が実際に支払った費用のことで,治療費や通院交通費などです。消極損害は,事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益のことで,休業損害や逸失利益です。慰謝料は,事故に遭うことで受ける肉体的・精神的な苦痛に対する賠償金です。
請求できる内容や注意点など,詳しくご紹介します。
消極損害その2 後遺症による逸失利益(42)
10.胸腹部臓器の障害
呼吸器(気管,気管支,肺,横隔膜等),循環器(心臓,心膜,大動脈等),腹部臓器(食道,胃,小腸,大腸,肝臓,胆のう,すい臓,ひ臓,腹壁等),泌尿器(じん臓,尿管,勝脱,尿道等),生殖器の障害に分けられます。
胸腹部臓器の障害の障害等級については,原則として,その障害が単一である場合には臓器ごとに定める基準により判断されます。また,その障害が複数認められる場合には,併合の方法を用いて相当級が判断されます。
(1)認定例
・ 女児(固定時3歳)の左腎機能全廃(13級11号)につき,残存する右腎臓にできるだけ負担をかけない生活上の不利益を受け,あるいは就労上の配慮を要するとして,賃金センサス男女計学歴計全年齢平均を基礎に,18歳から67歳まで9%の労働能力喪失を認めた。
・ セールスドライバー(固定時34歳)の腹圧性尿失禁(7級),射精障害(9級)の併合6級,骨盤骨変形12級,左下肢後面等;左大腿部側部・会陰部のしびれ12級の併合5級につき,腹圧性尿失禁及び左下肢等のしびれ等につき労働能力の喪失を認め,本人の努力や勤務先による内筋業務への配置転換,営業主任から安全推進係長や営業係長に昇格させる等の特別の配慮があるため減収なく700万円以上の年収を維持していることを考慮し,67歳まで60%の労働能力喪失を認めた。
(2)自賠責保険より高い等級や喪失率が認定された事例
・ 女子会社員(試用期間中,固定時40歳)の切迫性尿失禁・腹圧性尿失禁(自賠責非該当)につき,加齢を原因とすることは考え難く,初診時の超音波検査等から明らかな膀胱の収縮はないが膀胱容量が低下していることや,症状が薬剤による治療に対応した反応をしていることなどから,心因反応による症状ではなく,下部尿路を支配する神経損傷や骨盤内の膀胱尿道支持組織の損傷等に起因するとして11級10号と認定し,67歳まで20%の労働能力喪失を認めた。
愛知県では,愛知県警の取り締まり強化により,3年連続で交通事故死者数全国ワーストを脱却しましたが,未だ多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいます。
交通事故の被害に遭い,加害者に請求できる内容は,被害に遭われた方の症状や職業等によって,それぞれ変わってきます。
胸腹部臓器に後遺障害が残ると,身体を維持するための機能が働かなくなることが多いので,仕事や日常生活にも著しい支障が生じることになります。
しかしながら,臓器によっては,ただちに労働能力とは関係しないとして,逸失利益が否定されるケースもあります。
逸失利益は賠償項目の中でもっとも高額となりますので,適正な逸失利益を算定するためにも,ぜひ,弁護士法人しまかぜ法律事務所に,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。