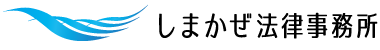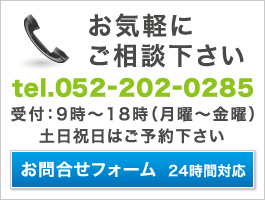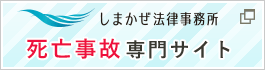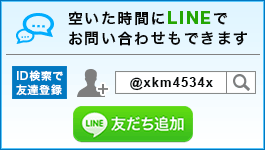Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:40歳,無職者に後遺障害14級9号が認定された場合
40歳,無職者(失業者)が交通事故により,むち打ちで後遺障害14級9号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,14級9号の場合,110万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,無職者(失業者)であっても将来的に就労の可能性があれば逸失利益は請求できます。裁判例の多くは,失業前の収入を基準に算定します。失業前の年収が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
後遺障害14級9号の労働能力喪失期間は5年間と認定されることが多いです。5年間のライプニッツ係数は4.3295です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.05×③4.3295=129万8850円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:40歳,会社役員に後遺障害14級9号が認定された場合
40歳,会社役員が交通事故により,むち打ちで後遺障害14級9号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,14級9号の場合,110万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
役員報酬には,Ⅰ労務対価部分と,Ⅱ利益配当部分の性格があります。会社役員の基礎収入として認定されるのは,Ⅰ労務対価部分での減額のみです。Ⅱ利益配当部分は後遺症によって労働能力が制限されても得られるため,基礎収入として算定されません。
もっとも,小規模会社や,サラリーマン役員など,役員報酬の性格が,Ⅰ労務対価が100%であると認定される場合は,役員報酬全額が基礎収入となります。
被害者が実際に労務を行い,例えば役員報酬が600万円と高額ではなく,従業員が数名と小規模であった場合,役員報酬全額が労務対価であって基礎収入です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
後遺障害14級9号の労働能力喪失期間は5年間と認定されることが多いです。5年間のライプニッツ係数は4.3295です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.05×③4.3295=129万8850円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:40歳,会社員に後遺障害14級9号が認定された場合
40歳,会社員が交通事故により,むち打ちで後遺障害14級9号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,14級9号の場合,110万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
事故前年の収入額です。源泉徴収票の税金等を控除される前の金額です。事故前年の源泉徴収票の金額が600万円であれば,基礎収入は,600万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
後遺障害14級9号の労働能力喪失期間は5年間と認定されることが多いです。5年間のライプニッツ係数は4.3295です。
以上より,逸失利益は,①600万円×②0.05×③4.3295=129万8850円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:40歳,個人事業主に後遺障害14級9号が認定された場合
40歳,個人事業主が交通事故により,むち打ちで後遺障害14級9号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,14級9号の場合,110万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
法人成りしていない経営者や,開業医,弁護士,保険外交員,一人親方,ホステスなど個人事業主の基礎収入は,事故前年の事業所得金額+事業専従者控除額or青色申告特別控除額で算定します。
事業所得金額が600万円,青色申告特別控除額65万円の場合,基礎収入は,665万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
後遺障害14級9号の労働能力喪失期間は5年間と認定されることが多いです。5年間のライプニッツ係数は4.3295です。
以上より,逸失利益は,①665万円×②0.05×③4.3295=143万9558円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:40歳,主婦に後遺障害14級9号が認定された場合
40歳,主婦(家事従事者)が交通事故により,むち打ちで後遺障害14級9号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,14級9号の場合,110万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
①基礎収入
主婦(家事従事者)の基礎収入は,女性労働者の学歴計・年齢計の平均賃金を参考にします。平成26年賃金センサスでは,364万1200円です。
家事をしながら仕事をしている方も多いと思いますが,ほとんどの裁判例では,仕事での賃金額を加算せずに,家事従事者の年収である364万1200円(平成26年賃金センサス)として認定します。
これは,主婦業は24時間労働であり,その主婦業全体の経済的価値を家事従事者の年収で評価したのであるから,その一部の時間を利用して仕事をしたとしても,それは主婦業の一部が仕事に転化したに過ぎないという理由です。
仕事の年収が,家事従事者の年収を超える場合は,仕事の年収で算定します。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
後遺障害14級9号の労働能力喪失期間は5年間と認定されることが多いです。5年間のライプニッツ係数は4.3295です。
以上より,逸失利益は,①364万1200円×②0.05×③4.3295=78万8228円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:18歳,男性,大学生に後遺障害14級9号が認定された場合
18歳,男性,大学生が交通事故により後遺障害14級9号が認定された場合,後遺症の慰謝料と逸失利益の賠償額ついて,説明させていただきます。
後遺症慰謝料は,14級9号の場合,110万円です。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定します。
事故当時アルバイト収入が年間100万円あった場合,学生時のアルバイトと卒業後に大きく分けて算定を行います。
Ⅰ学生時のアルバイト
①基礎収入
100万円です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
学生時の4年間です。それに応じたライプニッツ係数は,3.5460です。
以上より,学生時のアルバイトの逸失利益は,①100万円×②0.05×3.5460=17万7300円です。
Ⅱ卒業後
①基礎収入
逸失利益は,将来における収入減をみなしで請求するため,基礎収入は,将来可能性のある収入額を基準とします。
後遺障害14級9号は,労働能力喪失期間を5年間と制限して認定することが多いため,卒業後に会社員となっても,その基礎収入は,大卒・全年齢の平均賃金とするのではなく,大卒・22~24歳の平均賃金とするのが通常です。
男性・大卒・22~24歳の賃金センサスである321万4500円(平成26年賃金センサス)が基礎収入です。
②労働能力喪失率
後遺障害14級9号は,5/100です。
③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数
後遺障害14級9号の労働能力喪失期間は5年間であるため,終期は23歳です(18歳+5年間)。卒業後の始期は22歳です。学生時4年間を考慮してライプニッツ係数を算定する必要があります。
23歳-18歳=5年間のライプニッツ係数 4.3295
22歳-18歳=4年間のライプニッツ英数 3.5460
卒業後のライプニッツ係数 4.3295-3.5460=0.7835
以上より,卒業後の逸失利益は,①321万4500円×②0.05×③0.7835=12万5928円です。
後遺症が認定された場合,後遺症慰謝料と逸失利益が請求できますが,その金額は高額となります。高額となるがために,保険会社は低く抑えた賠償額を提示してきます。
適正な後遺症慰謝料と逸失利益を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について (神経症状)
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について,説明を連載させていただいていますが,第4回は,むち打ちによる神経症状です。
原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳として,労働能力喪失期間を算定します。
しかし,むち打ちが原因で,首や腰の痛み,手や足のシビレが残存したような神経症状で後遺症が認定された場合は,それほど長期にわたって回復が困難とは言えないとして,多くの裁判例では,12級13号は10年間,14級9号は5年間として労働能力喪失期間を制限して認定しています。
保険会社は,上記以上に労働能力喪失期間を制限して主張してきます。例えば,12級13号は7年間,14級9号は3年間と主張してきます。
しまかぜ法律事務所では,主治医に対して,労働能力喪失期間の医療照会を行うなどして,交渉に有利な証拠収集を行います。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について (高齢者)
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第3回は,高齢者です。
原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳です。67歳を超える高齢者はどのように労働能力喪失期間を算定するのでしょうか。
67歳を超える高齢者の労働能力喪失期間は,簡易生命表の平均余命の2分1とします。
簡易生命表は,「交通事故で後遺症を負った方へ」 をご覧ください。
また,症状固定日から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者についても,平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
例えば,症状固定日において72歳の女性・高齢者に後遺症が残った場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
簡易生命表(平成26年)女性・72歳の平均余命は18.10です。
したがって,労働能力喪失期間は9年間,これに応じたライプニッツ係数は,7.1078です。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について (若年者)
労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について,被害者の属性に応じて説明を連載させていただいていますが,第2回は,若年者です。
原則として,就労可能年数の始期は18歳,終期は67歳です。18歳未満の若年者の場合は,18歳になるまでを考慮して労働能力喪失期間によるライプニッツ係数を算出する必要があります。
例えば,症状固定日において12歳の若年者に後遺症が残った場合のライプニッツ係数は,以下のとおり算出します。
67歳-12歳=55年間のライプニッツ係数 18.6335
18歳-12歳=6年間のライプニッツ係数 5.0757
12歳被害者の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数 18.6335-5.0757=13.5578
なお,大学卒業を前提とする被害者の始期は18歳ではなく,大学卒業予定である22歳となります。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。
【コラム】:逸失利益の労働能力喪失期間によるライプニッツ係数について
後遺症が認定された場合,将来にわたって労働能力が低下して収入が減少するであろう損害(逸失利益)を請求できます。
逸失利益は,①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で算定しますが,③労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数について説明させていただきます。
労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数は,被害者の属性に応じて算定方法が様々ですので,属性に応じて説明を連載しています。
第1回は,原則としての労働能力喪失期間によるライプニッツ係数です。
被害者が,若年者でも高齢者でもない場合,原則として,労働能力喪失期間は67歳までの期間です。
ライプニッツ係数は「交通事故で後遺症を負った方へ 」をご覧ください。
逸失利益は,一般的に,もっとも高額な賠償項目となります。
適正な賠償額を獲得するためにも,豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所に,ぜひ,ご相談ください。

名古屋の交通事故に寄り添う「しまかぜ法律事務所」
名古屋は交通事故が多く、被害に遭われた方々が不安を抱えています。しまかぜ法律事務所は、そんな方々の力になりたいという思いから、交通事故に特化したサポートを行っています。
賠償額が適正か分からない、示談交渉が不安…そんなお悩みに寄り添い、解決へ導くことが私たちの役目です。相談料・着手金0円で、安心してご相談いただけます。名古屋・三重・岐阜で交通事故のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。